社員への手紙 その39
2011年5月10日 06:30
今回は、平成16年12月27日に書いた平成17年1月度の手紙です。
拝啓
今年も残りわずかとなってまいりました。昨日から寒さも一段と厳しくなってきて、年の瀬を感じさせるようになりました。風邪を引かないように健康管理には十分気をつけてください。この5、6年は正月工事が入っていたために、元旦は“現場で迎える”ことが恒例になっていましたが、来年の年明け1、2日は全員休めるようです。12月30日、31日、1月3日、4日は一部の方々にご協力いただいて工事を行ないます。赤チン災害も含め一切の事故や怪我の無い様に十分に気をつけて作業をして頂きたいと思います。ご家族の皆さんにもご負担を掛けるかと思います。ご理解とご協力をお願いいたします。
競争が大変厳しい今の時代に大切なことは、“我が社は一体何屋か?”、“お客様は私たちのどこを評価し、私たちを選んでいるのか?”ということを掘り下げて考えて、磨き上げていくことです。そこから私達の存在価値が生まれ、利益につながる付加価値が生まれてきます。今私達が持っている価値は、まず“機動力”です。特に食品業界のある程度まとまった量の工事を短期間でまとめあげることができる会社は、私達のような中小企業ではなかなか見つかりません。それを実現するには工事期間中の人間の確保はもちろんの事、全員が仕事の内容を理解して迅速に動けること、客先としっかりとした打合せを行い事前の段取りを綿密に行なう事、などなど様々な要因が必要となってきます。そして、そのためには全員がいつでもどこへでも出かけていくという全社協力体制をとれることが前提条件です。
お客様はいつもコストダウンを考えています。そのお客様が「金額を安くするために他の業者に頼もうか。」と思わせないようにしなくてはいけません。我が社は“ものづくり”の会社ですから、機械作りや現地工事などの分野に関しては、『品質・コスト・納期』面でお客様にメリットを生み出せるような提案できなくてはいけません。日向中島鉄工所に頼まないとうまくいかないから、しょうがないな。と思わせるものを持っていなくては、他社とコスト面での競争の末に原価割れの金額でも受注をするしかなくなります。全員が技能を向上させていくことも忘れてはいけません。どこに出しても恥ずかしくない品質の機械作りや工事を行なっていきましょう。
より強い競争力をつけていくために、年明けには営業と設計の人員を増やし体制を強化します。日向中島に話をすると“どんな相談にものってくれる。難しい問題も解決してくれる。かならずなんとかしてくれる”という信頼を得る事が大事です。「ものづくり」とそのマネージメント(品質・コスト・納期の管理)をノウハウとして確立して、メーカーやエンジニアリング会社と密接な協力関係を築き、お互いになくてはならないパートナーとなっていきたいものです。たとえ下請けの仕事であっても日向中島にしかない価値が認められれば、“主導権”を持って取り組むことができます。いままでの経験とノウハウに改善を重ねて、より一層積み上げていきましょう。
今年も一年間お疲れ様でした。ご協力頂きありがとうございました。良い年をお迎えください。来年も皆様にとってよい年でありますように! 全員でよい年にしていきましょう!
敬具
我が社だからこそできる事を磨いていこう! 自社の強みをはっきり意識し、それを徹底して伸ばしていこう!
ボランティア活動
2011年5月 9日 10:30
今回の東北大震災でも、多くの団体がボランティア活動をしています。 経済活動だけでは社会は回っていきません。 企業や行政だけではできない事も沢山あります。 それを補っていくのが、ボランティア活動だと思います。
そこで出逢う方々は、みなさん、とても素晴らしい方ばかりです。 みなさんが生き生きと活動をしています。 楽しんで活動を行うと共に、そこでたくさんのことを学んでいるのだろうと思います。 組織を超えたいろいろな方と出逢い、思いを共有し、自分の存在意義を確認しているのかもしれません。
それでは、企業の存在意義は何なのだろう、と考えさせられます。 かのP.Fドラッカーは、次のように言っています。 「企業の目的の定義は一つしかない。それは、顧客を創造する事である」「会社は社会の一員であり、『社会のニーズを満足させる』=『顧客を創造する』ためにある。」
これまでの高度成長の時代とは違い、これからは、企業と行政と非営利組織と住民が一緒になって地域の活性化のためのそれぞれの役割を果たしていかなくてはいけないのではないかと思います。
そういう意味で、これからも地域の活動と企業活動の双方を一生懸命行っていきたいと思います。
以上です。
東日本震災復興 チャリティイベント in 清武
2011年5月 8日 06:00
昨日は、清武町で行われた“東日本震災復興チャリティイベント”に参加をしてきました。
てんつくマンの講演と、東日本震災の復興支援活動の報告会がありました。 てんつくマンの自分に正直な生き方と行動力と熱い思いに改めて感動しました。
講演も非常にパワフルで、来場者の心に届く言葉を沢山発信していました。 私もプロジェクター操作役でスタッフの一員で参加でき、とても楽しかったです。
てんつくマンは、今度の大震災も現場に行く事が一番学べる、心を育てるチャンスだから、ぜひ行って、何かを感じ、何ができるのかを考えて欲しいと、言っていました。
どんな日本を子供たちに残すのか? 子供たちに諦めない姿を見せよう!と語りかけました。
心に残った言葉を書きとめました。
・ 自分に具体的な問いかけをし、具体的な行動をしよう。
・ 道がなかったら作ればいい。新しい常識を作ればいい。
・ 今日という日は、残りの人生の最初の日。
・ 絶対無理という言葉に惑わされる必要はない。
・ できるかどうかではなく、やりたいかやりたくないか。
・ 絶対あきらめない、と腹を括ることで、未来は開ける。
・ 自分に誇りを持った時、必ず花が咲く。
・ 全ての出来事は良い出来事、
全ての出逢いは良き出逢い。
・ 未来を作っているのは、今の気持ち、
前を向く気持ちが大切。
・ 苦しい時は、心が育つチャンス。
・ 人生は団体戦。助け合い・支え合い・一緒に幸せになろう。
・ 人は、ありがとうと言われる事がうれしい。
誰かの力になれる事が、自分の喜びになる。
・ 言葉はすごい力を持っている。
肯定的な言葉は未来を変えれる。
だからこそできる事は? 良い意味で・・・
・ よくある事・よくある事。修行・修行。
・ 一億二千万人の三歩で日本を元気に!
・ NOを語るより、YESで行動し、YESを広めよう。
また、多くの方との出逢いがありました。 色々な場で一緒に活動をして、宮崎を盛り上げていきたいと思います。
以上です。
みやざき『食と人の支援』連合チーム
2011年5月 7日 11:00
昨日は、みやざき『食と人の支援』連合チームの打合せを行いました。
これまで、南九州商事・ぐんけい・宮崎文化本舗が一緒になって、東北の支援を行ってきました。 これから先の活動の仕方を宮崎アートセンターで話し合いました。
みやざき『食と人の支援』連合チームは、そもそも肉巻きおにぎりの販売や旅行会社を経営している南九州商事さん単独での支援活動から始まりました。 南九州商事の社員さんの中に、東北出身の方がいて、社長に会社を休んで支援に行きたいと相談をしたところ、社長が会社全体で支援をしていこうと決断をし、社業の肉巻おにぎりの炊き出しで、被災地支援を始めたそうです。
会社から肉巻きおにぎりの移動販売車を出し、原材料費等の一切の経費を含む全額を会社が負担し、4月の初旬から、毎日2000食のおにぎりの炊き出しをしています。
現地では、会社の名前も出さず、宮崎からの支援ということで活動をしている事、社業への影響もあるなか、少しでも支援を継続したいと他人のために動きまわっている事、を聞いて、感動しました。 どうしてそこまでできるのか? この人はどこを見て、動いているのか? 身近にもすごい人がいるもんだ、と感じています。
企業単独の活動では、公的機関も支援できないため、“ぐんけい”さんや宮崎文化本舗さんが賛同をし、チームを作り、活動を開始しました。 我が社も少しでも力になれればと思い、チームに名を連ねさせて頂きました。
こういう時に生き様が見える気がします。 自分の人生をどう生きたいのか? 何のために生きているのか? 誰のために生きているのか? 自分も使命感を感じて生きていきたいと思います。 息子に生き様を示し、想いが伝わるような生き方がしたいと思います。
以上です。
営業技術部 組織改革
2011年5月 6日 08:30
5月1日から、営業技術部の組織改革をしました。
これまで営業技術部の中にあった営業課と設計課を統合し、営業技術部全員で仕事を作り、仕事を取りに行くための体制作りです。 お客様との接点の少ない部門では、社内の事、自分の事ばかり考えるようになってしまいます。お客様や市場の事を見ずに、自分の都合ばかりを主張するようになってしまいます。 特に技術やテクニックを必要とされる部署では、そのこだわりを追求するあまり、何のためにその技術があるのか? 誰のおかげで自分の仕事があるのか? という根源的な問いは忘れがちです。
仕事がある事が当然と考えるのではなく、もう一度、原点に戻り、お客様から何が必要とされているのか? お客様に我が社が必要とされるためには、私たちはどうあるべきなのかを考える機会としてもらいたいと考えています。
そういう意識ができてきた後に、そのために、技術を磨く事を再度行えば、お客様に喜んで頂き、なくてはならない会社になると思います。
それと並行して、設計の3DCAD化を検討しています。 2DCADは、製造のための設計思想や仕様の図面化です。 一方、3DCADは、使い方によっては、サプライチェーンを縦に結ぶ情報共有ツールになる可能性があると考えています。 しかし、3DCADを導入するためには、これまでの2DCADの作図テクニックを捨てなければいけない部分もありますので、技術者にとって、とても辛いことだと思います。
日本人の細かい神経とものづくりに関する優秀さがあるゆえに、あたらしい技術への乗り移りが遅れる事を懸念しています。 手書きからCADに移った時もそうであったように、それぞれの技術の良いところ、悪いところがあり、古い技術に習熟している優秀な技術者ほど、移行が遅れる傾向があります。 世界の中で、ガラパゴスにならない様に、お客様のためになる技術かどうかとの見極めとイノベーションへの追従を行っていきたいと思います。
”転がる石にはコケはつかない。” 肯定的にとらえ、変化を厭わず、いつも新しい事に挑戦をしていく組織になりたい、と思います。
以上です。



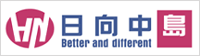

最近のコメント