高鍋トークライブ収支報告
2011年3月26日 06:30
昨日は、夢を語ろう!トークライブin高鍋の収支報告会でした。
2月13日のトークライブから1ヶ月と少しが過ぎようとしているなか、会計担当に収支報告を取りまとめて頂きました。
1か月という短い準備期間の中、あの場に来てくれた参加者の方々に、多くの物を残し、そして、収支面でも赤字を出すことなく、終了する事ができました。
スタッフとして参加して頂いた方々、お一人お一人に感謝の言葉しかありません。
昨日も、会の目的の話になりました。 発端は、多少なりとも残った収益の中から活動費を残していった方がいいのか? それとも、寄付金や支援のために全額使用した方がいいのか? という議論からでした。 そのなかで、この会を長く存続させ、自分達の考える活動を続けていくためには、多少の活動費は残していった方が良い。 そもそも、収益を残す事が目的ではなく、また、単にイベントを行う事でもなく、地域が元気になるきっかけをつくっていきたい、ということだから、いつでも動き出せるための資金は必要だ、という意見が主流だったと思います。
今回も、鳥インフルエンザや新燃岳の災害で被害を受けた皆さんと一緒に、私たちに何ができるのか? 何をするべきなのかを考えよう、という目的で講演会を行いましたので、義援金は、いくらかは生み出せましたが、金額の多寡ではありませんでした。 大勢の方々が会場に足を運び、多くの方々が何かを感じて頂いただけで、その目的は果たしています。
今回実行委員会に集まった皆さんが東北関東大震災のための支援物資を持ち寄ってきました。 そして、大分の仲間に託しました。 収支報告会の間も東北の方々に向けてのメッセージ作成の時間になっていました。
その時々で、私たちのできることを考え動いていくチームであれば、それでいいと思っています。 とっても熱く語り、行動する仲間と、これからも地域が元気になるように、活動をしていきたいと、改めて思いました。
以上です。
退職年金制度説明会
2011年3月25日 09:00
我が社も、適格年金制度から、確定給付年金制度に移行しました。
移行時に一度説明会を開催しましたが、その内容を理解してもらうためには、一回では不十分で、理解が進むまで、回を重ねて説明をしていきたいと考えて、今回2回目の説明会を開催しました。
従業員の皆さんに、現在の退職年金制度の現状について知ってもらうと共に、自らの老後の資金について関心を持ってもらうための説明会でした。 日本生命さんにとても細かい資料を作って頂き、社員の皆さんに1時間ほどで説明をして頂きました。
制度の移行は行いましたが、社員全員の退職金が確保できているわけではありません。 もし、いま社員全員が退社ということになった場合は、当然退職金原資は不足します。 これから、みんなでその財源を積み上げていかなくてはいけない、ということも理解してもらわなくてはいけません。
これまでの適格年金制度は、5%の利回りが前提となっていたということと、積み立てた額が退職までの期間が短い人に先に支払われて、これからまだ先の長い人の退職金が確保できていないという問題がありました。
確定給付型に移行すると共に、原資が不足している退職金を積み立てていく必要があります。
厚生年金も、これから受給開始の時期が繰り上げられていきます。 もらう方は、心配の方が先に立ってしまいます。 しかし、お金の心配もありますが、元気なうちは、お金の事だけでなく、体を動かして働く事はいいことだと思います。 我が社でも希望者は65歳迄来て頂いています。 昔の65歳と比べて、今の方々は、とっても元気だと思います。 60歳を過ぎて自宅で時間を持てあましているようだととってももったいないことです。
退職後の資金の事をそれぞれが考えるようになるために、これからも説明会を開いていきたいと思います。
以上です。
ミツバチの羽音と地球の回転
2011年3月24日 07:00
先日21日に映画の上映会に行ってきました。
「ミツバチの羽音と地球の回転」という映画です。 山口県上関原発建設が進められる中、地元の方々の反対運動を描き、原発推進の是非を問いかける映画です。
一次産業により生計を営む住民の生活と伝統を伝える神舞というお祭り、原子力発電所の建設を進めようとする中国電力や行政と地域住民の方々との衝突、長い歴史の中で素朴な生活が営まれている地域に原発建設を進める事の不条理さ、横暴さを描いています。 同時に、スウェーデンのあるオーバートーネオという都市では、自然エネルギーによってエネルギーの自立をしようという努力を続け、電力の半分は自然エネルギーでまかなっているという事実も紹介しています。
私たちは、ひたすら便利な生活、物質的に豊かな生活を追い求めてきましたが、このままでは、持続可能な社会は作れないということは、はっきりしてきました。 資源やエネルギーや食糧など、欲望のままに使い続けることには限界がある事が見えてきました。
改めて、生きる意味だとか、幸せや豊かさの意味について考え、今持っている価値観を根本から見直す必要がありそうです。
映画の中に多くの印象的な言葉があります。
どうして日本が石油を買い続ける事ができるのか、わからないよ。
バリアーを外すんだ、新しいエネルギーを阻むものの。
問題を起こすより、解決する方がよっぽど楽しいよ。
すべてがコンビネーションなんだ。
映画の中に、ひとりの市議会議員さんが登場します。 市議の仕事はボランティアとしてやっています。 「金のかからない良い事を、ずっと持続可能性について考え続けてきました。」という彼女は、ボランティアだからこそ、低予算で持続可能な環境プロジェクトに関わり続けられるのだ、と思いました。 本来の政治のあり方を見せてもらった気がします。
いま、私たちは、経済優先の社会中で、目標もなく走り続けるのではなくて、一度立ち止まり、周りを見回し、自分の立ち位置を確認してみる必要があると思います。 もしかすると経済優先で走り続けている先には、深い崖があり、明るい未来にはつながっていないのかもしれません。
今回の映画は、改めて色々な事を考えさせてくれるとともに、今自分達の未来をしっかり選択し、行動に移していかなくてはいけないと、気付かせてくれるものでした。
最後に、この映画のタイトルの意味を。
「世界にあるどんな小さなことでも、影響を及ぼしているのだ。 たとえばどこかでミツバチの羽音がしたとしよう。 するとその羽音は、地球の回転にさえ影響を及ぼしているかも知れないのだ」
以上です。
こころざし課題図書(平成22年9月度)
2011年3月23日 07:00
“こころざし”平成22年8月度の課題図書は、ビジョナリーカンパニー③ / ジェームズ・C・コリンズ 著でした。 その時の感想文を掲載します。
1.衰退の5段階
今回の課題図書、ビジョナリーカンパニー衰退の5段階を読み終えて、なぜ衰退の過程を細かく分析する必要があるのか、少々疑問に思った。組織の衰退を早い時期に見つけ出し、進路を転換させるということだと思うが、自社がどういう状況にあるか?という事が問題では無くて、自社で大事にすべき事が守られていないために衰退への道をたどっているという事自体が問題である。その根本的な問題についてまず考えるべきであり、常に自問すべき事であると思う。
2.道に迷う方法
道に必ず迷う方法というものがある。そのための3つの条件とは、以下である。①自分がどこに行きたいのかわからない。②自分がどこにいるのかわからない。③目的地までの道順を書いた地図を持っていない。
つまり、これらのものを事前に準備していれば、道に迷う事はない、ということだ。起業した当座は、しっかりとした理念やビジョンを描き、それに向かって進んでいたのだが、道を進むうちに、どちらへ向かうのか忘れてしまった。また、自社の存在価値は何なのか?いま自社はどういう状態にあり、何を求められているのか?という事が市場や客先の目線から考えられているのか?そもそも道を間違っているのではないか?どこかに迷いこんでいないか?根本的なところで間違っているのではないか?
衰退の段階を細かく分析する事は、どこで道を間違ったのか、地図のどこにいるのかを考える様なものだと思う。もっとも大事な事は、行く先はどこなのか、そもそもの理念やビジョンに沿った経営ができているのか、という事を考えることではないのか?
3.規律という事
成功から生まれる傲慢、規律なき拡大路線、リスクと問題の否認、一発逆転策の追求、転落か消滅という5段階があるといわれるが、どれも原理原則に逆らって、自社の都合のみで動いた結果ではないか?
規律という事は規則やルールを守るという事もあろうが、理念や基本的価値観に沿った行動を守る、原理原則を外さず行動するという事を言っていると思う。そのためには、企業内で自社の理念を大事にして、その浸透に全力をつくすという社風や企業文化が大事になると思う。
4.3方よしの経営
本書の付録の事例が非常に参考になる。
ディミッコは、「事業は進化していかなければならず、その際に基本原則が揺らがない様にしなければならない。顧客への関心を高め、顧客の要求をつねに進歩のきっかけにし、社内の判断基準を確立した事が進歩を促すカギとなった」といっている。また、ブレーク・ノードストロームは、「顧客サービスの最優先、改善への情熱、起業家的な労働観、等の基本理念を維持し、進歩を促す」としている。
100年企業が世界で最も多いといわれる日本企業が大切にしてきた3方良しの思想と経営姿勢は世界に通じるものだと思う。経営者が常に謙虚で、高い志をもって、理念を追求する事の大切さを物語っている。
ブレーク・ノードストロームの言葉が心に残った。「会社の衰退が我々の責任である事はあきらかだと考えている。経営者が一番下に位置し、顧客と販売員が一番上に位置する逆ピラミッド型の組織構造を確立日、会社の問題に対する責任を受け入れた。」経営者の姿勢、理念や哲学の欠如、志の欠如が衰退のもっとも大きな原因だと考える。
その覚悟が社内に伝われば、まさに規律のある会社であり続けるのだと思う。
会社も人生もしっかりしたビジョンや目標を持っているかどうかで、モチベーションや行動も変わる。 会社の将来像をいつも社員さんに語りかけるとともに、個人的な目標ともすり合わせていきたいと思います。
以上です。
社員への手紙 その28
2011年3月22日 06:30
今回は、平成15年12月26日に書いた1月度の手紙です。
拝啓
寒冷の候、年の瀬に向かい慌しい毎日をお過ごしのことと思います。年末らしく寒さが厳しくなってきました。風邪がはやっていますが、体調を崩されないようにご自愛ください。今年は、一部の方を除いて、最低3日の休みは取れそうです。甲斐正喜さん、川﨑薫さん、片桐建男さん、中島陸夫さんには、大変御苦労をかけます。高崎への出張工事のため1日しか休めませんが、体に気をつけ無事故で頑張って頂きたいと思います。
今年は、大変厳しい年でした。数多くの中小企業が倒産や廃業をし、多くの失業者を作りました。大企業はリストラを繰り返し、多くの従業員の犠牲を踏み台に何とか回復基調を作り出しました。公共工事はさらに減少することが予想されています。繰り返しお話しているように経済自体が縮小していく中で、仕事量が減っていくことは避けることが出来ないことです。昨年より今年、今年より来年、仕事のやり方も中身もレベルアップしていかなくては、減少していく仕事量や単価をカバーしつづけることは出来ません。常に変わりつづけることが大事です。小さなことの積み重ねが大きな変化を生み出します。
1月から2月にかけて、希望する方に、CADの講習を受けさせるという案内をしました。図面を読みとる力、平面的な図面から実物を思い描く力が大事だとの考えからです。忙しい合間ではありますが、この講習に限らず、常に自分の能力を磨いていくために、多くのことに挑戦して頂きたいと思います。お金の面でも時間の面でももっともっと自分に投資すべきです。会社もできる限りの応援をしていきます。
「松下電器は何を作っているところか?」と尋ねられた松下幸之助が「松下電器は人を作るところでございます。あわせて電気器具もつくっております。」と答えたと言う逸話が残っています。「事業は人にあり」、つまり人が養成され、能力を向上しつづけなければ、事業は成功するものではない。という考え方を表したものです。厳しい時代になればなるほど、その会社に勤める人一人ひとりの真価が問われる時です。会社の売上や利益は会社の総合力に対する評価と行ったことへの対価でしかありません。
厳しい環境になればなるほど、原点に戻る必要があります。
いま我が社が持っている「動員力」「誠実に取り組む姿勢」が、これからますますお客様に評価される時代になっていくと思います。これらの特徴を強みとして発揮するために全員の力の結集が必要です。来年こそみんなの頑張りを成果に結び付け、みんなで分け合えるようにしたいものです。
新しい年が、皆さんにとって、良い年になりますように!
敬具
会社の力は、人の力。 人の力は、考え方×熱意×能力で発揮される。
能力は、日々の積み重ねで身についていくもの。 熱意は、なりたい自分ややりたい事がはっきり描けた時に湧き出てくるやる気やモチベーション。 考え方は、何のために働き、生きるのかという価値観や意識。 人間力を上げていくしか、会社が繁栄する方法はない。 そう痛感する毎日です。
以上です。



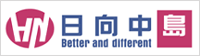

最近のコメント