東北関東大地震
2011年3月21日 08:00
震災の発生から10日が経ちました。 現場の状況は報道されている以上に悲惨な個所がたくさんあるようです。
しかし、その中から、力強く立ち上がろうとしている方々も大勢いらっしゃいます。 また、全国に支援の輪が広がっています。
昨日は、西都でおこなわれた“このはなマラソン”に出場したあとに、ボランティア・リーダーの鹿児島のみゆきさんのお話を聞く事ができました。
マラソンもチームメッセンジャーの方々の後から最後尾で走って、皆さんとともに、10kmを完走しました。
その後に、場所を移動して十数名の方々と一緒に、災害復興ボランティアのお話を聞きました。 これまでも様々な地域で復興支援をしてきた方ですので、現場の状況を分かりやすく、的確にお話しいただき、状況がよくわかりました。
結論は、現地の情報をできる限り詳細に知って、現場での活動を後方から支援をしなければいけないということ、そして、そのためには、民間レベルで、もっと横のつながりを作っていかなくてはいけないという事です。
これまでと違って、今回は町の機能が全壊の状態だから、行政機能もマヒし、復興に必要な“炊き出し”“復興センター”“流通センター”も立ち上がっていないとの事でした。 どこに避難場所があるのかもわからない状況のようです。 てんつくマンなどが現場の状況を伝えてくれていますが、現場の声を拾う多くの人が必要だということでした。
そして、私たちは、その情報にすぐ応えていかなくてはいけません。 これからは、現地の実情に合わせた細かい支援も必要になるといいます。 こちらからも現地の声に即座に対応できるようにしたいと思います。
昨日は、中長期的な事も話もでました。 住む場所・働く場所をなくした方々を全国でいかに受け入れていくのか、農業者が不足している地域とうまくマッチングできないか、など、
産業界としても、何ができるのかを、考えていきたいと思います。
以上です。
情報社会
2011年3月20日 06:30
今回も、エジプトのお話は、休憩です。
あまりにも東日本大震災の影響が大きく、様々な事を考えさせられてしまいます。
エジプトやリビアや、東北関東大地震に共通して、特に最近感じるのは、インターネットを通じての情報が非常に大きな重要性を持ってきているという事です。
テレビや新聞の通じての報道は、様々なところへの配慮をしながらのものにならざるをえないので、真実をストレートに報道する事ができなかったり、一部の組織の意思を考慮した偏ったものになったりする可能性があります。
それに比べて、インターネットでは、何のフィルターもかからないまま、発信されることで、個人的な意見レベルのものも載せられてしまいますが、真実がそのまま伝わってくると言えます。
一部の偏った考え方に影響されないためには、さまざまな意見を聞きながら、できる限り自分の頭をニュートラルな状態に保つ努力をしなければいけません。
そのためには、ツイッターやフェイスブックなどによって発信される情報にアクセスして、より多くの情報に接すると共に様々な方面の本を読んで、考える力を付けたいと思います。
最近、植草一秀さんの「日本の独立」という本を読んでいます。 とっても衝撃的な内容です。 日本社会の表に出ていない部分のことを考えるととても怖くなります。 何事も正と負の両面あると共に、受け止め方・考え方によって、どちらにもとらえられます。 良い面に光を当てて、良い面を引き出すようにしたいものです。
そして、負の面がある事も確かですが、人の意見や情報に引きずられることなく、自分が想像し、描いた明るい未来に向かって、できることから行動に移していきたいと思います。
本日は以上です。
取引銀行のこと
2011年3月19日 16:00
弊社取引銀行の担当者が転勤となりました。
銀行員の方々の転勤サイクルはとっても早いです。 親交が深まり、会社の事も良くわかってもらった頃、突然の転勤がやってきます。 挨拶や気持ちの整理もつかないまま、慌ただしく異動になるようです。 さまざまなメリットもあるようですが、本人は辛い事もたくさんあるだろうなあと思ってしまいます。
先日は、転勤が決まり週末までに引っ越しをしなくてはいけないということで、最後の日の1時間だけ時間をとってもらい、お話をしました。 短い間ではありましたが、さまざまな思い出があり、とくに勉強会の設営などで一緒に活動をしたことは、とても楽しい思い出です。 寂しさもぬぐいきれません。
歴代の支店長・担当者の方々とは、異動になってしまうとなかなかお会いする機会がありません。 その中で、毎年6月に行われる合同経友会という会は、みなさんにお会いできる数少ない機会ですので、とっても楽しみにしています。
企業にとって、金融機関とのお付き合いは欠かすことができません。 日頃の運転資金や大きな投資で資金が必要となった際には、金融機関さんのお力が必要となってきます。 だから、日頃から自社の事を良く知ってもらい、経営方針を知ってもらい、必要な資金を必要な時に用立てしてもらえる関係を作っておくことが必要になってきます。
そういう意味で、我が社は創業以来一行とのお付き合いを続けてきて、さまざまな面で支援をして頂いています。
中小企業家同友会で、金融アセスメント法案の制定活動をしています。 特に地方金融機関は、我々中小企業にとっては生命線です。 地域経済の活性化のために、血液の循環をよくするという役割を果たして頂きたいと考えています。 もちろん私達企業も、投資した分でしっかり価値を生み出す努力をしなければいけない事はいうまでもありません。
以上です。
新入社員教育カリキュラム
2011年3月18日 12:00
今年は、新入社員のカリキュラムを作っています。
これまでも入社後2週間程度は新入社員教育を行ってきましたが、十分ではないと考えていました。 しっかりとしたカリキュラムを作る必要性を感じていました。
今春、4名の大学生が入社します。 これから5年後、10年後の我が社を見通して、若手社員の層を厚くしておくことが目的です。
日本のものづくりは、現場力は強いが、ホワイトカラーの生産性が低いと言われています。
現場の職人や技術職に支えられている面もあります。 しかし、これからは、その力に企画開発力や新しいものを生み出す力を育てていかなくてはいけません。 現場力と企画開発力の融合が求められています。
今年は、60名の会社で4名の採用ですから、かなりの思い切った先行投資です。 そして、今後もあたらしい人材を継続して多く雇用していきたいと思っています。
しかし、もちろん彼らの力だけで会社が変わるものではありません。 採用活動を通じて、会社がこれからどこに力を入れようとしているのか? どの方向に向かおうとしているのかを社員さんに明確に伝え、全社が力を結集されるきっかけにしたいと思っています。
今年からブラザー制度を取り入れる予定です。 この制度は、多くの会社ですでに取り組んでいますが、我が社はこれまで採用が不定期だったため、これまで行ってきませんでした。 ブラザー制度によって、新入社員への細かいフォローができるということ以上に、先輩社員に生まれる自覚と高い意識を期待しています。 採用や教育に関わることで、自社全体を見直し、自分を見つめ直す社員さんを増やしていきたいと思っています。
また、新入社員教育カリキュラムも作っています。 これから社会人として生活をし、仕事をするうえで大切なことについて、考える機会を多く作りたいと考えています。 実務的な事は、これからOJT やOff-JTでいくらでも時間が取れるので、この期間には考え方や姿勢等、基本的な事を重点的に行っていこうと思います。
日本生命さんによるルーキーズ向けお金の基本講座も行いまず
以上です。
経友会例会 植松さん講演会
2011年3月17日 10:00
先日、鹿児島銀行経友会の例会で、植松さんの講演会が行われました。
今回で5回目となりますが、毎回とても感動的なお話です。 胸がじ~んと熱くなります。 自分の人生体験を通して、現代の問題を深く分析し、社会への問題提起をされています。 「ど~せ無理!」 という言葉で、人の可能性を否定する事をやめよう、という訴えかけは、植松さんの心からの叫びに聞こえます。
植松さんの言葉は、一つひとつとても重く感じられます。 講演の中から心に残った言葉を記録しておきます。
大量生産、大量消費に支えられた社会から、転換を図らないと日本は生き残っていけない。
1から100を作りだす仕事ではなく、0から1を生み出す仕事を増やしていこう。
いやな状態を、誰かのせいにしても、何も変わらない。
いやな状態は、何でいやなのか? だったらこうしてみたら?と考えたら発明になる。
小さな追求が奇跡を生み出す。
やってみたい事、したい事を追い求めると成長する。
未知に挑むと能力が増える。
常に「more」を求める環境は、よい修練の場。
お金で買わず、自分で学べ。
失敗したら、どうすればいいのか一緒に考えよう。
失敗を、自分のせい、誰かのせい、何かのせいにしない。
なんでだろう、だったらこうしてみたらと考えよう。
一生懸命とは、一生やめないという意味。
責任とは、成功するまでやり続ける事。
楽を選ぶと無能になる。能力は経験からしか身につかない。
芸は身を助ける。中途半端だって何もしないよりはいい。
真の金儲けは、「価値」を生み出すこと。
本と出逢い、人と出逢おう。
関わる人によって、「普通」は変わる。良い仲間をさがそう。
やりたい事は、やった事がある人から学べばできるようになる。
走り続ければ、仲間が見つかる。
リーダーシップとは、責任と判断を駆使して、先駆けてやること。
「特別」だと必要とされる。もともと人は特別な存在。
人は知恵と工夫で世界を救うために生まれてきた。
思い描く事ができれば、それは現実にできる。
Dream can do, Reality can do.
“理想”は、目標を見失わず、やり続けるための、“北極星”
植松さんは、今年の10月13日(木)、14日(金)に、日向市中小企業振興計画の
「ものづくり講演会」で、再度講演をして頂く予定になっています。 これまでに聞いたことがない人はぜひ聞いて頂きたい講演です。 特に小さいお子さんを持った方、学校の先生方、これから社会を背負っていく若者達、お待ちしています。
以上です。



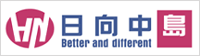

最近のコメント