こころざし課題図書(平成22年8月度)
2011年3月16日 06:30
“こころざし”平成22年8月度の課題図書は、生物と無生物のあいだ / 福岡 伸一 著でした。 その時の感想文を掲載します。
今回の課題図書は、読み物として非常に面白く、二つの面で興味深く読める本だった。一つは、文章の巧みさである。その場にいる様な気にさせる細かい描写は、情景が目に浮かぶようでぐいぐいと引き込まれた。もうひとつは分子生物学の世界の出来事を単なる時系列、歴史上の事実としてではなく、登場人物の思いや感情を感じさせながら描いている事。とても面白く読ませてもらった。
ただ、レポートを書くとなると話は別で、何回か読み返しながら、自社の経営やこころざしの活動にどう引き寄せて考えるかということに頭をひねった。
1.動的平衡について
人の体のタンパク質は、つねに置きかわているという。体のありとあらゆる部位、臓器や組織だけでなく、骨や歯ですら、絶え間ない分解と合成が繰り返されている。人間という肉体がダイナミックな流れの中にあるという。もっというと、肉体という個体自身が外界と隔てられた個物としての実在ではなく、密度の高い分子の「淀み」でしかないという。
世の中の全てのものが、形を変えながら存在するだけで、全ての個体の分子レベルでの総数やエネルギーの総量に変化はない、という事も言われるが、まさにその事の意味がこの動的平衡ということなのかと思う。
私達の体自身が動的平衡のもと、常に流れの中にある存在だとした場合、私達の個人個人が持つエネルギーの違いや活力の差はどこから生まれるのか? 個体自身がもともと持つエネルギーにそれほど大きな差があるとは思えないが、それをつき動かすなんらかの原動力により生み出す力には、なぜか大きな差がうまれる。
思いや気というものは、確かに存在しているのだろうと思う。
“生命とは動的平衡にある流れである”との文章があるが、もっと広く解釈をすると、この世の中にあるすべてのものが動的平衡の中にあり、固定され安定している物など何もないということではないか?
そう考えると、上昇する動きや変化をおこすために、常にプラスのエネルギーを投入していくことが、大事な事であろうと思う。
2.チャンスは準備された心に降立つ
以前、グッドラックという本がベストセラーになった事がある。
チャンスは、万人に平等に降り注ぐ。しかし、それを生かせるか生かせないかは本人次第で、日頃から土を耕し、種をまき、肥料や水をやっている等の準備をしている人だけがチャンスを生かせるというストーリーだった。まさに、日頃から問題意識を持ち、アンテナを張り、準備をしている人のみがチャンスに気付き、チャンスを生かせるのだと思う。
3.生命を燃やす
福岡氏の言うとおり生命は動的な平衡状態の事であるとすれば、常に変わり続けるという事が生きるということかと思う。近年上昇や成長・発展よりも安定や平穏を求める傾向が強いように思うが、“生きている
生命は絶えずエントロピーを増大させる“ということからも、成長発展を目指す方が自然なことのように思う。短い人生の中で、生命を燃やし続けたいと思う。
すべては、必然と考えると、何事も前向きにとらえられる。 すべてのことは、なにか意味があって起こっている。 まるで意志があるかのごとく、大きな流れ沿って動いている。 そうであるならば、個人的な感傷や感情に流されず、その流れや大きな法則に身をゆだねてみるのも、一つの生き方だと思う。 自分の思いや願いを大きく広げて細事にこだわらず生きていく事ができるようになればと思っている。
以上です。
社員への手紙 その27
2011年3月15日 07:00
今回は、平成15年12月1日に書いた12月度の手紙です。
拝啓
寒冷の候、年末に向かい慌しい毎日をお過ごしのことと思います。出張や休日の出勤が多くご本人はもちろんのこと、ご家族の皆様にも大変なご負担をおかけしていることと思います。風邪など引かないようにご自愛ください。
現在はこれまで誰も経験したことが無いような大変な不況だということが言われ続けてきました。しかし一方では、これは不況ではなく普通の状態だ。という意見もあります。今は不況だが、これを乗り越えるとまた景気はよくなるという風に考えると、大きな間違いを起こすことになりかねません。
景気に関係なく、少子高齢化という問題は間違いなく進行していきます。特に大量の食糧・車・生活消費財・住居などを必要とする若年層や勤労世代は2020年までに3割減るという統計が出ています。
あらゆるものを今までのように作りつづけ、消費していくことは不可能です。高度成長の時期は、どんどん仕事が入ってきて、大勢の人間で次々に仕事をこなしていけば右肩上がりの成長が望めました。
しかし、景気が良くなる事を期待して今までのやり方を辛抱して続けていけば何とかなる、という考え方を変えていかなくてはいけない時期に来ています。
我が社の中でも世間と同じことが起こっていると考えなくてはいけません。我が社がお客様から評価を受けている点に“動員力”があります。特に工場の運転休止期間中に短い工期で、効率よく仕事ができるという点が評価されています。受注量が多く確保できているときには強みとなっていましたが、一方で設備投資が減り、仕事量が減ってくると人が多いということは、また弱みにもなりかねません。
残念ながら我が社の人件費率は非常に高くなっています。社外に依頼する仕事の割合、外注比率が高くなっていることも拍車をかけています。昨年の我が社の外注費は全体の売上の3割に達しています。この点をどう解消していくのか、全員で考えていかなくてはいけません。
一般的に考えられる方法には以下のものがあります。①他が出来ないような技術や製品で勝負し、一人あたりの付加価値をあげる。(全員が自分の仕事の能力を上げる努力と共に仕事の改善を継続して行う)②製造原価をできる限り下げる。(一人が何役もこなし、外注を減らし、社内で行う仕事の比率を増やしていく)③固定費を削減する(少数精鋭・人件費の削減)
もう一度経営指針書を見直し、自分がすべきことを振り返ってください。
全員の雇用を守るためには、賃金の見直しも含めて検討することも考えなくてはいけません。大変厳しい時代ではありますが、前向きな努力を重ね、頑張っていきましょう。
今年も残りわずかとなりました。一致団結して良い年を迎えましょう。
敬具
自分で読み返しても、年末に向かい、気を引き締めたいと考えながら、書いている事を感じます。 今更ながら、危機感が伝わってきます。 いつも危機感を感じながら経営をしてきました。 それを社員の皆さんに伝えるすべを知らず、ひたすらストレートに語りかけてきたような気がします。
以上です。
東北沖大地震について その3
2011年3月14日 06:30
日を追うごとに、地震による被害の甚大さが明らかになってきました。
昨日は、東京のお客様とお話をしました。 報道で伝えられる被害と共に、経済や産業への損害も大きい事を改めて考えさせられました。
まず、住居に加えて、工場や公共施設、ライフラインなどのインフラも徹底的に破壊されている事。 市民の生活の見通しが立たないため、工場の再開のめども立たない事。 地域としての復興に全力を尽くさなくてはいけないため、これからの施策や設備投資は、東北中心になること。 今回の地震による影響は、我が地域や我が社へもかなりあると考えておかなくてはいけません。
東北地方の少しでも早い復興のために、自分達に何ができるのかも考えて、素早く実行をしていきたいと思います。
節電、物資の送付、献血、募金・・・・・他
昨日は、てんつくマンたちが大阪で東北沖大地震支援イベント「今、僕たちにできること」を行いました。 その中で今すぐできることを話していましたので、このブログにも載せておきます。
---------- ---------- ----------
1、携帯ラジオ(単三電池使用のもの)
2、ペンライト(単三電池使用もの)
3、単三乾電池(6本セットで販売しているもの)
<送り先>
〒578-0963
東大阪市新庄3-21-47
会津通商 大阪営業所
電話番号 06-4309-1880
商品名 3点セット※分かりやすいようにしっかり明記して下さい。
<注意点>
・3点はできるだけコンパクトにまとめてお送りください。
・生ものやワレモノは送らないようにお願い致します。
・当分は、上記の3点をより早く被災地にお届けする予定ですので
他の物資については、同封しないようにお願い致します。
○●○●○●○●
募金はこちらに振り込んでいただけたらありがたいです。
○●○●○●○●
※支援金は下記の口座にお願いします。
(郵便局で備付けの用紙でお願いします)
天国はつくるもの基金宛
郵便振替 口座番号 00120-5-425716
口座名称 天国はつくるもの基金係
通信欄に「東北地方太平洋沖地震支援金」と記入してください
よろしくお願いいたします。」
イベントの中で、山田バウさんが言っていた言葉が心に残ったので、書き留めておきたいと思います。
まず、動け。すべての事は学習だよ。 すべての事から、学ぼう。 自分の心の中に愛を感じてみよう。
自分の向上心を球のように立体的にイメージした方が良い、どの方向でも良いから、とにかく動いて、感じる事。
以上です。
宮城沖地震その2
2011年3月13日 07:00
時間を追うにつれ、被害の大きさが明らかになってきました。 地震による家屋の倒壊や津波による被害に加えて、石油備蓄基地の火災や原子力発電所の放射線漏れなど、東北の方々が被られた被害の大きさは想像を絶するもののようです。
現地の方々は、未だ続く余震と津波の恐怖の中で不安な生活を続けているかと思います。
昨年は、ものづくりシンポジウムや同友会経営フォーラム等で、宮城の方々にも日向市に足を運んで頂きました。 とても連絡が取れるような状況ではないかと思いますが、安否が心配です。 口蹄疫の時には、全国から沢山の励ましと応援を頂きました。 とても他人事と思えません。 義援金・物資の提供等できる限りの事をしていきたいと思っています。
昨日、会社から家に帰ると、部屋の電気を消して食事の準備をしていました。 ツイッターからの呼びかけに応じて、節電をしようと考えてのことでした。
まず、身近なできることからやる、考えながら行動することが大事かと思います。
インターネットやツイッターからの情報には、真偽が不明のものも含めてさまざまなものが含まれているため十分に気を付ける必要がありますが、現地の状況を自らのこととしてとらえ、素早く行動に移そうとしている善意を持った人々の情報も多く含まれています。
一つ一つをしっかり考え、やるべきだと判断をしたら、躊躇せず行動に移していきたいと思います。
また、同時に私たちも日向灘で地震が発生した場合の事も想定しておく必要がありそうです。
以上です。
宮城県沖地震
2011年3月12日 18:12
今日は、朝から津波対策の復旧でバタバタしていたため、アップが遅くなりました。
昨日、宮城県沖地震が起きました。 時間を追ってその惨状が繰り返し、報道されています。 被害に会われた方に心からお見舞いを申し上げます。
我が社では、地震が起きた時間には、2012年度卒業予定の学生さんを対象に、一次選考会を行っていました。 17時に、津波の第一波が宮崎に達し、その大きさは2mと予想されるとの報道があり、急遽社員全員を集め、仕事を切り上げ、帰宅するように指示を出しました。 もちろん一次選考会も日を改めて行うことにし、中断をしました。
我が社のある場所は、細島港から数百mしか離れていずすぐ横には海につながる小さな川も流れているため、その後、日向市から避難勧告の連絡もありました。 津波が襲ってきた後の事も心配だったので、社用車の高台への避難、パソコンの2階会議室への避難、出張者等への連絡を済ませ、17時10分前に、会社を離れました。
実際には、予定より少し遅れて1mの津波が2回ほど到達したようでした。
今日の朝一番で、海沿いにあるお客様の守衛所に行ってきました。 そこは、常に水位をモニターでチェックしているそうですが、2度の津波もそれほど、大きな水位の変化はなかったとおっしゃっていました。
しかし、油断は禁物です。 今日は宮崎方面と延岡方面に行ってきましたが、一部の国道十号線では、通行止めになっていました。 いまだ津波警報が出されたままになっています。
テレビの報道も繰り返し詳細に現地の状況を伝えてくれていますが、インターネットやツイッタ等での情報発信も役に立っているようです。 また、お互いに被災時の対応方法や何かできる事はないか?という内容のメールも飛び交っています。
東北の方々はとても大変な状況かと思いますが、頑張って頂きたいと思います。 私にもできることをやっていきたいと思っています。
以上です。



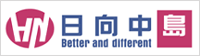

最近のコメント